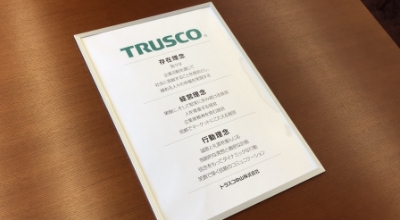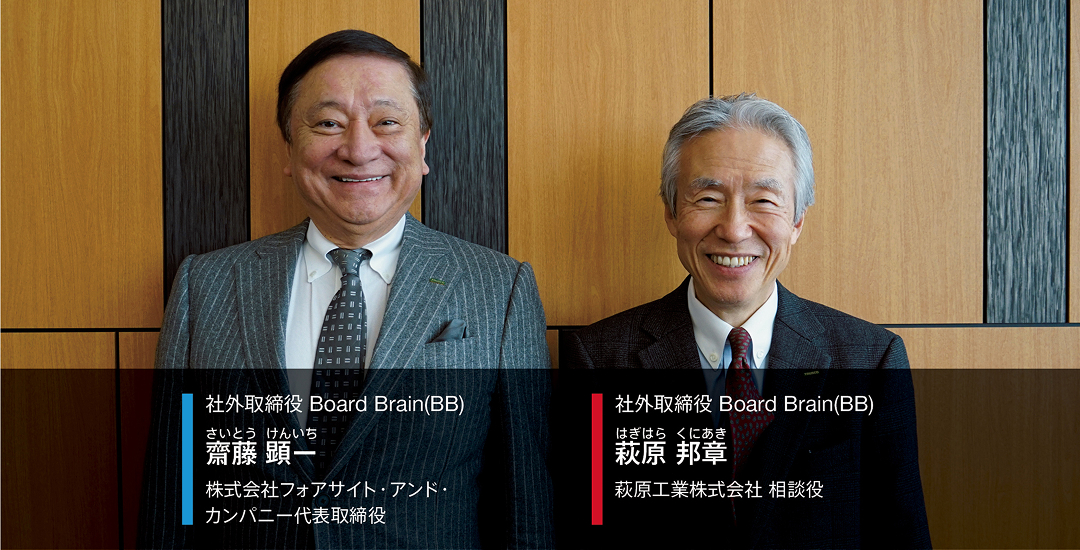
社外取締役候補者 梨田 昌孝 社外取締役 大田 梨沙
豊富な経験や知識を生かし、当社の発展に貢献してもらうことをイメージして、当社では社外取締役をボードブレーン(Board Brain、通称BB)と呼称しています。一般的には外部の目として「不祥事の防止」を役割とする場合が多いのですが、当社では透明性の高い独自のガバナンスを形成しているため、「持続的な成長・企業価値の向上」への貢献に重きを置いています。その社外取締役各氏に、ご自身の豊富なご経験や知識に基づいたご助言をいただきました。
ご自身のご経験や知識がトラスコ中山の社外取締役に、どのように活かせるとお考えでしょうか。
梨田
私はチームビルディングを長く経験してきましたので、風通しの良い社内を作ることに貢献できると考えています。
社内のいろいろな立場の人が、意見を言い合えるような環境作りが大切です。特に立場のある人から社員、パートさんに積極的にコミュニケーションをとることが大切で、私は監督をしていた時に、選手は勿論ですが、トレーナーや通訳の方とも対話することを重視していました。アイデアや良い意見を得られることも多く、またそういったポジションにいる方々のモチベーションの向上にもつながります。
大田
私はメーカーと商社の機能を持つ中小企業で取締役をしており、その知見を活かし様々な立場から助言をしていきたいと思っています。
日本の99.7%が中小企業で、日本で働いている約70%の人が中小企業に勤務していると言われています。実際の現場はどのようなものかというと、人が足りない、時間も足りない、そしてリソースも足りないと、足りていないものばかりです。そして、これらをどう効率よく回すかを模索しています。購買に関しても、大企業であれば購買担当の方がいて、そこに上司もいて、若手もいて、といったように教育や改善にもリソースをかけることができていると思いますが、中小企業となると、色々な業務と兼任をしながら購買を担当している人が多いです。このような時にはこれを買いなさい、といった指示や指導があるわけではありません。特に製造業は、製品の開発や生産にリソースをかけているので、購買管理まで手が回っていないことが多く、その為、どこから調達したらよいか分からない、何を選んだらよいか分からないという声も多くあります。そういった時に当社のカタログやシステムは活躍すると思います。こういったリアルな現場の声を伝えていきたいと思います。
組織運営や人材育成に関して多くのご経験があるかと思いますが、様々な能力や年代の選手がいる中で、指導や助言をする際に意識されていることはありますか。
梨田
やはり人によって全然性格が違いますので、相手に合わせた伝え方をする必要があります。この人はやる気を引き出すために褒めてあげた方がいいだとか、この人にはストレートに叱ってあげた方が良いだとか、人前で怒られたくない人もいますし、相手に合わせた伝え方を見極めることが大事です。また、監督をしていた時に意識していたのは、選手は18歳~35歳くらいと年齢が幅広いので、話をする際に相手によって伝え方を変えることです。18歳の選手と話すときは18歳の目線に合わせた話をしていますし、35歳の選手に向けては、チーム全体の打ち合わせ前にあらかじめ答えを準備させることもしました。こういった話をするからと事前に伝えておくことで、打ち合わせ中に後輩たちの前で的確な発言をしてくれます。野球でもチームが優勝する時は、小さな個人の力が集まって、一束になり、「モンスターワンチーム」となり、想像もできないような大きな力になりました。それを私は何度も経験してきました。プロの世界でも会社でも、メンバーのやる気をいかに引き出すかが1番大切だと思います。多くの人のやる気を引き出すことができれば、やはり大きなチームの力になります。

モノづくり企業の視点で、当社事業への期待はございますか。

大田
やはり当社のように在庫を揃えているのは、製造業から見てとても有難い事です。困った際にまず最初に聞いてみよう、という流れになります。私も会社で何かが足りない、となった時にまず"トラスコさんにあった?"と聞きます。そうすると、 "トラスコさんに在庫ありました"、という返答が大体返ってきます。このようなやり取りをよくしています。また中小企業では、購買業務におけるプロセスが確立されていないことに本当に困っています。属人的な経験だけで業務を回している現場も多いはずです。業務が体系化されていないと担当者が辞めてしまった場合に、購買が回らなくなってしまうので業務のシステム化は必要です。ただ、単に制度やツールを導入すれば良いという訳でもなく、現場の人間が意欲を持ってそれを運用してこそ意味があります。当社は在庫や自社のインフラを利用した色々なサービスをモノづくり業界に提供していますので、それらの浸透を図り、今後も様々なユーザー様に頼られる会社となってほしいと思います。
当社の社員へのメッセージをお願いします。
大田
最近入社された社員は、トラスコという看板が用意されたところに入社してきているので、自分が恵まれた環境にいるということをぜひ意識してほしいと思います。営業に行った際にお客様にスムーズに出迎えてもらえるのは、個人の力というより会社の力であることが多いです。会社の看板がなくなった時に、同じパフォーマンスを出せる人は少ないと思います。個人の力を高めることを意識していくことが、会社全体を前に進めることにつながります。
梨田
会社の看板によって自分の能力をカンチガイしてしまう人もいると思います。仕事をしていく中で、会社の看板のおかげで、下手に出てくれるような相手もいると思います。ただ、下に来られたらもっと下に出るくらいの態度が大事だと思います。私は常に自分より年下の人でも、尊敬の気持ちを忘れずに接するようにしています。そして、若い時はそういったことをしっかりと教育してもらうことが大切だと思います。 教育、と捉えると難しいと思いますが、私が勧めたいのは誰か目標となる人を見つけることです。野球のプレーであったら、あの先輩の真似しよう、ノートを書くのであれば、この選手が分かりやすく書いているな、このように自分の目標となる人を見つけましょう。先輩、後輩関係なく、周りを見て、あの人の様になりたいとイメージすることで、同じ様になれなかったとしても、少しでも近づけるように努力が出来ると思います。当社で働く社員達も、一緒に働く周りの社員に目標としてもらえるような働き方ができるよう意識できたらより良いのではないかと思います。